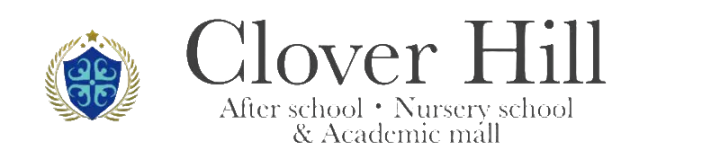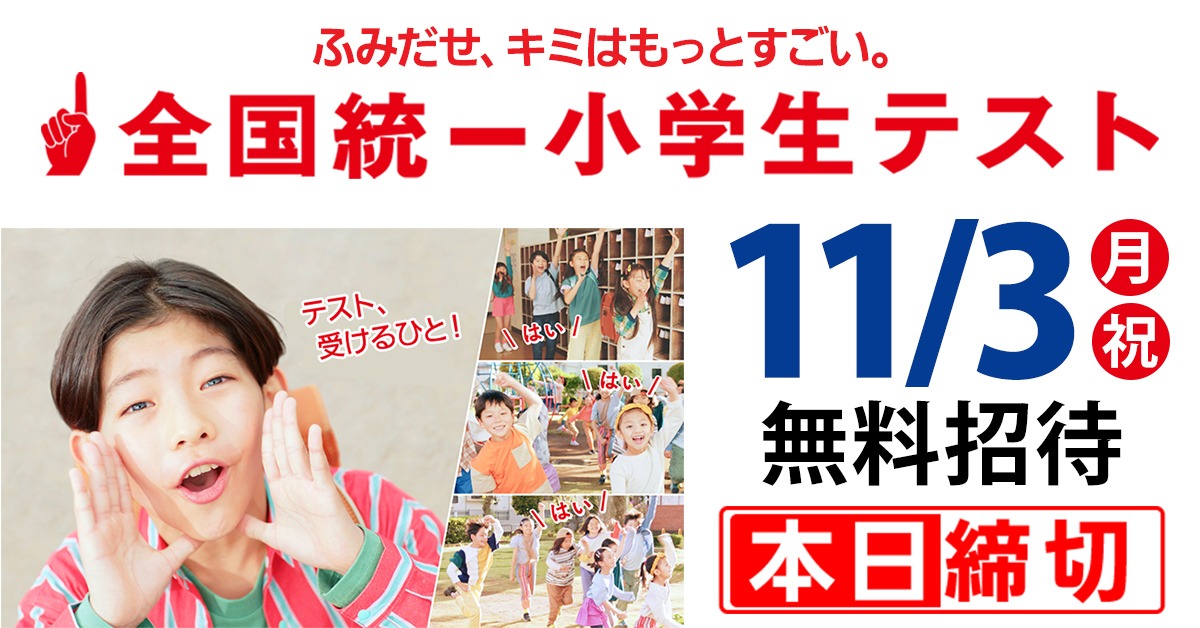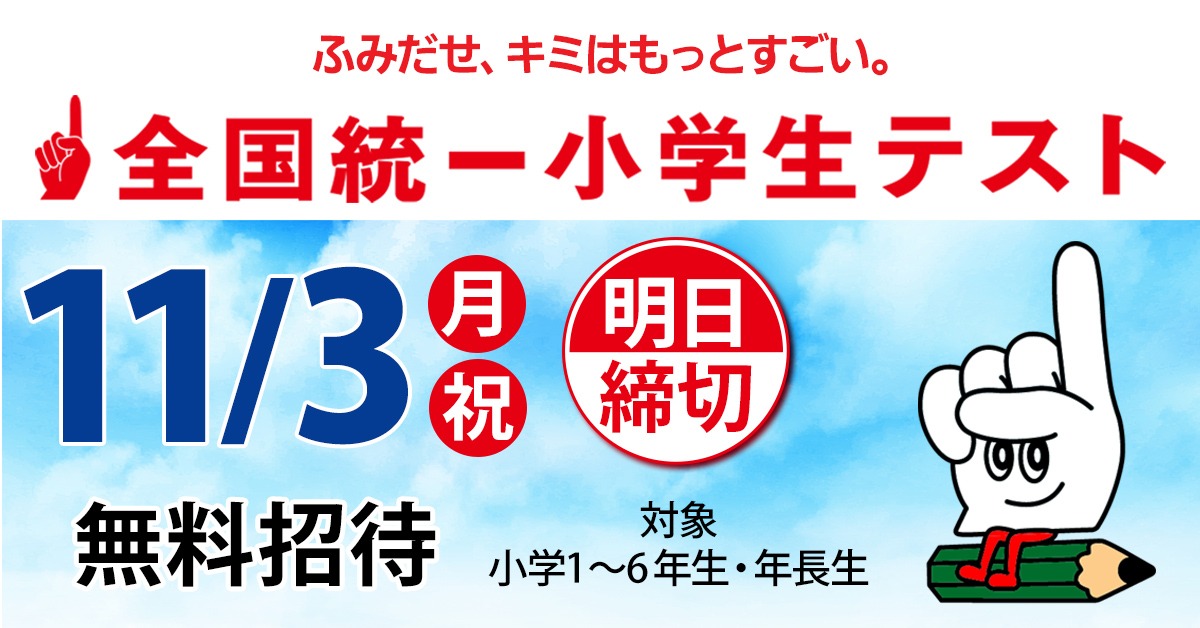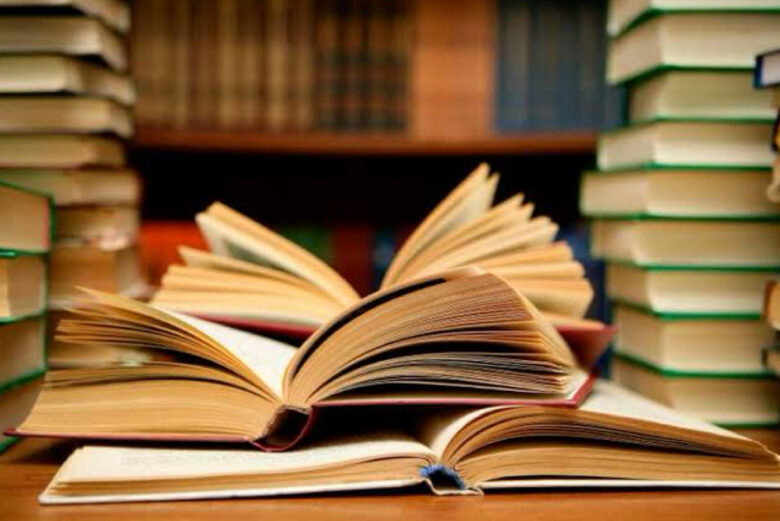公立中学進学予定の小学6年生が全国統一小学生テストを受験する7つの本質的メリット~保護者が知るべき教育的価値と活用法~|府中市の教育複合施設CloverHill

Contents
- 1 はじめに:公立進学予定者こそ受けるべき「全国統一小学生テスト」の真の意義
- 2 メリット1:全国規模の客観的データで「現在地」を正確に把握できる
- 3 メリット2:中学校の学習スタイルへのスムーズな移行を促進
- 4 メリット3:無料で受けられるハイクオリティな学力診断
- 5 メリット4:学習意欲向上と自己肯定感の育成
- 6 メリット5:中学校の授業に対応するための基礎力診断
- 7 メリット6:親子で取り組む「学習習慣」確立のきっかけ
- 8 メリット7:高校受験を見据えた長期的な学力育成
- 9 全国統一小学生テストを最大限活用するための5つの実践的アドバイス
- 10 よくある質問と専門家の回答:公立中学進学予定者のためのQ&A
- 11 まとめ:公立中学進学予定者こそ受けるべき全統小の本質的価値
- 12 府中市・府中第二小学校隣の教育複合施設Clover Hillのご紹介
はじめに:公立進学予定者こそ受けるべき「全国統一小学生テスト」の真の意義
「全国統一小学生テスト」(以下「全統小」)は、中学受験塾の四谷大塚が主催する日本最大規模の学力テストで、毎年6月と11月に実施され、1回あたり約15万人が受験します1。一般的には中学受験を目指す生徒が受けるイメージが強いこのテストですが、実は公立中学進学予定の小学6年生こそが受けるべき本質的な価値が数多く存在します。
本記事では、公立中学進学を予定している小学6年生の保護者に向けて、全統小を受験する7つの本質的メリットを徹底解説します。表面的な「偏差値がわかる」「無料で受けられる」といった情報ではなく、お子様の長期的な学力形成と自己成長にどのような影響を与えるのか、教育的観点から深掘りしていきます。
特に重要なのは、このテストが単なる「学力測定ツール」ではなく、「学力を伸ばすための仕組み」として設計されている点です2。テスト前の対策授業、テスト中の緊張感ある環境、テスト後の詳細な分析と見直し指導まで、一連のプロセス全体がお子様の学力向上に寄与するよう工夫されています。
公立中学進学予定者にとって、この時期に全国規模の客観的な学力診断を受けることは、中学校生活へのスムーズな移行と、その後の高校受験に向けた確かな土台作りに不可欠です。以下では、具体的な7つのメリットとその活用法を詳しく見ていきましょう。
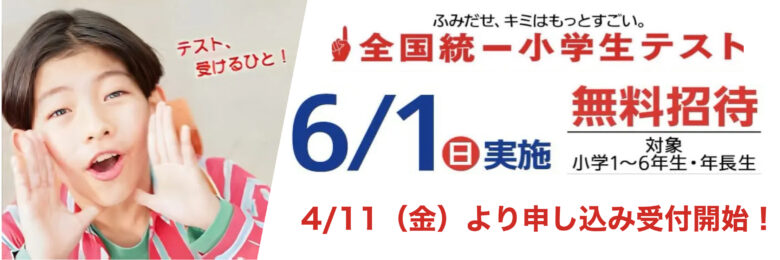
東京都府中市府中市立府中第二小学校となり
教育複合施設Clover Hill
メリット1:全国規模の客観的データで「現在地」を正確に把握できる
公立小学校だけではわからない「真の学力レベル」が明らかに
公立小学校のテストでは、基本的に「授業で習った内容が理解できているか」を確認するための「到達度テスト」が中心です。100点を連発する生徒も少なくありませんが、これは「学校の授業内容を理解している」という意味であって、全国的な視点で見た時の相対的な学力レベルを測るものではありません8。
全統小では、全国の小学6年生(約15万人)という膨大な母集団の中で、お子様の学力がどの位置にあるのかを偏差値や百分位(上位何%か)で明確に示してくれます1。公立中学進学予定者にとって、これは極めて貴重な情報です。なぜなら、中学校に入ると定期テストで校内順位がつき、高校受験では明確に競争が始まるからです。
「うちの子は学校のテストではいつも90点以上取っているから大丈夫」という安心感は、実は危険な錯覚かもしれません。全統小を受験することで、全国的な視点での「真の学力レベル」を客観的に知ることができ、中学校進学前に適切な対策を講じるきっかけが得られます。
「問題別成績一覧表」で弱点を科学的に分析
全統小の最大の特徴は、単なる順位や偏差値を知るだけでなく、「問題別成績一覧表」という詳細な分析資料が提供される点です1。この資料には、各問題ごとの全国正答率とお子様の正誤が一覧で表示されるため、以下のような分析が可能です:
- 基礎力不足の特定:正答率80%以上の基本問題で間違えた場合 → 根本的な理解不足が疑われる
- 応用力の課題発見:正答率30-70%の中程度問題で間違えた場合 → 応用問題への対応力に課題
- 得意分野の確認:正答率30%以下の難問で正解した場合 → 突出した能力がある可能性
公立中学進学予定者にとって、この「科学的な弱点分析」は中学校の学習にスムーズに適応するための貴重な指針となります。特に小学6年生のこの時期に自分の苦手分野を自覚しておくことで、中学校の授業が始まる前に重点的な復習が可能になります。
表:問題別成績一覧表の活用法
| 正答率 | お子様の結果 | 示唆される課題 | 具体的な対策 |
|---|---|---|---|
| 80%以上 | 不正解 | 基礎的な理解不足 | 該当単元の教科書レベルの復習 |
| 30-70% | 不正解 | 応用力不足 | 標準レベルの問題集で演習量を増やす |
| 30%以下 | 正解 | 高い潜在能力 | 更に発展的な学習に挑戦させる |
都道府県別ランキングで地域内での位置も確認
全統小の成績表では、全国順位だけでなく「都道府県別順位」も確認できます1。これは公立中学進学予定者にとって特に重要な情報です。なぜなら、高校受験は基本的に「都道府県内」での競争になるからです。
全国的に見れば平均的な成績でも、居住地域によっては上位に入る場合もあれば、逆に「この地域のレベルは高い」と気づく場合もあります。このデータは、将来の高校受験を考える上での貴重な基礎資料となります。
メリット2:中学校の学習スタイルへのスムーズな移行を促進
「長時間のテスト慣れ」が定期テスト対策の基礎を作る
全統小の小学6年生の試験時間は3時間30分にも及びます1。これは公立小学校のテスト時間(通常45分程度)とは比較にならない長さです。この長時間のテストに集中して臨む経験は、中学校の定期テスト(1日で複数教科実施)や、将来的な高校受験に向けた貴重な「慣れ」となります。
多くの公立中学進学予定者が中学校に入って最初に直面する壁が「定期テストの長さと分量」です。小学校のテストとは異なり、中学校の定期テストは:
- 1教科あたり50分程度
- 1日で複数教科実施
- 問題量が多くスピードが要求される
こうした変化に対応するためには、小学6年生の段階で一定程度の「テスト慣れ」が必要です。全統小は、単に学力を測るだけでなく、こうした「テストそのものへの適応力」を養う場としても機能します。
マークシート形式への早期適応が高校受験優位に
全統小では小学3年生からマークシート方式が採用されています1。公立小学校ではほとんど経験しないマークシート形式に慣れておくことは、将来的な高校受験で大きなアドバンテージとなります。
マークシートには独特のコツが必要です:
- 解答欄のずれ防止(1問解くごとにチェック)
- 時間配分の最適化(途中で詰まったら飛ばす判断)
- 消しゴムの使い方(完全に消さないと機械が誤認識)
これらのスキルは、いきなり高校受験で求められてもすぐには身につきません。小学6年生のうちからマークシート形式に慣れておくことで、高校受験時に余計なストレスを感じずに実力を発揮できるようになります。
4教科バランスの「見える化」で中学校準備が可能
全統小では小学4~6年生が国語・算数・理科・社会の4教科を受験します1。公立小学校ではあまり意識されない「4教科のバランス」を客観的に把握できるのは、公立中学進学予定者にとって大きなメリットです。
中学校では主要5教科(英語が加わる)のバランスが成績に直結します。特に公立中学校の場合、内申点(調査書点)が高校受験に影響するため、特定教科の極端な苦手は避けなければなりません。全統小の結果から:
- 理科・社会の暗記分野が弱い
- 算数の図形問題に課題がある
- 国語の長文読解が苦手
こうした傾向を早期に発見し、中学校入学までに重点的に対策することで、スムーズな中学校生活のスタートが切れます。
メリット3:無料で受けられるハイクオリティな学力診断
塾に通わなくてもプロの分析が無料で受けられる
全統小の最大の特徴の一つが「無料で受験できる」ことです1。市販の学力テストや模擬試験は通常3,000~5,000円程度かかることを考えると、非常にコストパフォーマンスの高い学力診断と言えます。
特に公立中学進学予定の場合、塾に通っていない家庭が多いため、専門的な学力分析を受けられる機会が限られます。全統小では、塾に通わなくても:
- 詳細な偏差値と順位
- 単元別の得意・不得意分析
- 全国規模での相対評価
こうしたプロレベルの分析を無料で受けられるのは大きなメリットです。四谷大塚が無料で提供する背景には「塾を知ってもらうためのイベントとしての側面」があることは事実ですが1、保護者がそのことを理解した上で利用すれば、純粋に学力診断ツールとして活用できます。
市販テストでは得られない「全国規模」のデータ精度
書店で購入できる市販の学力テストと全統小の決定的な違いは、「母集団の規模と質」です。全統小は毎回約15万人が受験する日本最大規模のテストであり1、そのデータの信頼性は市販テストとは比較になりません。
特に公立中学進学予定者にとって、全国規模の正確なデータに基づく分析は貴重です。なぜなら:
- 母集団が大きいほど偏差値の信頼性が増す
- 地域偏りが少なく全国的な位置が正確にわかる
- 問題の難易度分析が精緻(正答率データが豊富)
こうした高品質なデータを無料で得られるのは、保護者にとって見逃せないメリットです。
テスト後の充実したフォローアップ体制
全統小は「テストを受けて終わり」ではありません。受験後には以下のような充実したフォローアップが無料で提供されます2:
- 解説動画:四谷大塚のホームページで1週間限定公開される解説動画で、自宅で復習可能
- 見直し勉強指導:希望する会場では、テスト後に講師から個別のアドバイスが受けられる
- 君だけの診断レポート:単なる成績表ではなく、今後の学習アドバイスが記載された詳細な分析レポート
公立中学進学予定者にとって、こうしたプロの指導が無料で受けられる機会は貴重です。特に「見直し勉強指導」では、間違えた問題について「三段階前まで遡りながら原因分析」するため7、根本的な理解不足を解消するきっかけが得られます。
メリット4:学習意欲向上と自己肯定感の育成
「目標設定→達成」の成功体験で学習意欲が向上
全統小は年に2回(6月と11月)実施されるため1、これを定期的な目標として設定することで、お子様の学習意欲を高めることができます。特に公立中学進学予定者にとって、明確な目標がない小学6年生後半は学習意願が低下しがちな時期です。
「次の全統小で算数の偏差値を5上げる」といった具体的な目標を設定し、それを達成する経験は:
- 自己効力感(「やればできる」という自信)を育む
- 計画的に学習する習慣が身につく
- 中学校の定期テスト対策の予行練習になる
教育心理学では「適度な挑戦目標」が学習意欲を高めることが知られています。全統小は、お子様にちょうど良い挑戦目標を提供する絶好の機会です。
全国規模の競争が「もっと頑張ろう」という気持ちを刺激
公立小学校ではあまり経験しない「全国規模の競争」に参加することは、お子様のやる気を刺激する効果があります。全統小の成績表には「全国順位」や「都道府県順位」が明確に記載されるため1、自然と「もっと上を目指したい」という気持ちが芽生えます。
実際、テストを受けた子供が「全国の精鋭たちが競い合い、高め合う場」を経験することで、その後の勉強に対するモチベーションが飛躍的に向上するケースが多いと報告されています2。特に「競争心」が強いお子様の場合、このような外部刺激は学習意欲を高める有効な手段となります。
「解ける喜び」が知的探究心を育む
全統小では、学校のテストよりも少し難しめの応用問題も出題されます1。これらの問題が解けた時の「達成感」や「喜び」は、お子様の知的探究心を大きく刺激します。
ある保護者は、子供がテスト後に「算数の最後の問題が面白くて!」と楽しそうに話し、「問題を楽しんでいるのがうれしかった」と感想を述べています5。このようなポジティブな体験は:
- 学習そのものへの興味を深める
- 自発的な学びの姿勢を育む
- 難しい問題に挑戦する意欲を高める
公立中学進学予定者にとって、このような「学ぶ楽しさ」を体験できる機会は貴重です。中学校以降のより高度な学習に向けて、知的探究心の土台を作ることができます。
メリット5:中学校の授業に対応するための基礎力診断
小学校範囲の総復習機会として活用できる
全統小の出題範囲は「各学年で習う内容」が中心です1。つまり、小学6年生が受けるテストでは小学校で習う全範囲が対象となります。これは公立中学進学予定者にとって、小学校内容の総復習を行う絶好の機会です。
中学校の学習は小学校の内容が基礎となっています。特に:
- 算数(数学の基礎)
- 国語(全教科の読解力基盤)
- 理科・社会(中学校の専門的内容の前提)
これらの分野で小学校内容に穴があると、中学校の授業についていけなくなる可能性があります。全統小を受験することで、小学校範囲の総まとめと弱点発見が同時に可能になります。
「中学への橋渡し」となる重要な単元を重点チェック
全統小の問題を分析すると、中学校の学習に直結する重要な単元がよく出題されます。例えば:
表:中学校学習に直結する小学校単元の例
| 教科 | 重要な単元 | 中学校での発展内容 |
|---|---|---|
| 算数 | 分数の四則計算 | 代数計算の基礎 |
| 算数 | 比と比例 | 関数の概念へ発展 |
| 国語 | 論説文の読解 | 社会科・理科の資料読解 |
| 理科 | てこの原理 | 物理の力学分野へ |
| 社会 | 日本の産業 | 地理・公民分野へ発展 |
全統小の結果からこれらの単元の理解度を確認し、必要に応じて復習することで、中学校の学習準備がより確実なものになります。
中学校教師も注目する「真の学力」がわかる
公立中学校の教師は、入学してくる生徒の「真の学力」をある程度把握しています。学校のテストで良い成績を取っていても、応用力や思考力に欠ける生徒は、中学校の授業で苦労する傾向があります7。
全統小では、単なる知識量だけでなく:
- 知識を活用する力
- 情報を選択・組み合わせる力
- 新たな思考を展開する力
こうした「真の学力」が測定されます2。このような力を小学校卒業前に把握しておくことで、中学校の授業スタイルに適応するための準備が可能になります。
メリット6:親子で取り組む「学習習慣」確立のきっかけ
テストを軸にした「学習リズム」を作りやすい
全統小は年に2回定期的に開催されるため1、これを利用して家庭学習のリズムを作ることができます。特に公立中学進学予定の小学6年生にとって、この時期に自律的な学習習慣を確立することは、中学校生活への円滑な移行に不可欠です。
具体的な活用方法としては:
- テストの2ヶ月前:目標設定(例:算数の偏差値を55に上げる)
- 1ヶ月前:過去問に取り組み、苦手分野を明確化
- 3週間前:苦手分野に特化した学習計画を立てる
- 1週間前:総復習と時間配分の練習
- テスト後:結果分析と次の目標設定
このようなサイクルを半年ごとに繰り返すことで、自然と計画的な学習習慣が身についていきます。
父母会で得られる「プロの教育アドバイス」
全統小の多くの会場では、子供がテストを受けている間に「父母会」が開催されます57。ここでは教育の専門家から貴重なアドバイスが得られ、公立中学進学後の子育てに役立つ情報が得られます。
実際の父母会で話される内容の例:
- 中学校の学習内容と求められる力
- 効果的な家庭学習の方法
- 思春期の子供との接し方
- 高校受験の最新情報
ある保護者は父母会に参加した後、「『勉強嫌いにはさせないで!』と塾側からのメッセージがひしひしと感じられました」と述べ、子供の学習意欲を損なわない教育の重要性を再認識したと語っています5。
親子のコミュニケーション深化の機会に
全統小は親子で取り組む価値のある共同プロジェクトです。テストの結果について話し合うことで:
- 子供の得意・不得意を共有理解できる
- 目標達成の喜びを共に味わえる
- 今後の学習方針について建設的な対話が生まれる
ある保護者は、テスト後に子供と結果を分析し、「まずは褒めてから、前向きな声掛けをする」ことの重要性を実感したと述べています5。このようなポジティブな関わりは、親子関係を深めると同時に、子供の自己肯定感を高める効果もあります。
メリット7:高校受験を見据えた長期的な学力育成
中学1年生からのスタートダッシュを可能に
公立中学進学予定の小学6年生が全統小を受験する最大のメリットの一つは、高校受験を見据えた長期的な学力育成が可能になる点です。中学1年生の最初の定期テストで好成績を収めることは、その後の学校生活と高校受験に大きなアドバンテージをもたらします。
全統小の結果を活用すれば:
- 小学校範囲の最終チェックができる
- 中学校の学習に直結する弱点を補強できる
- 適切な学習習慣を確立できる
これら3点を小学6年生のうちに達成しておくことで、中学1年生の4月から好スタートを切ることが可能になります。
高校受験で求められる「真の学力」の基礎を作る
公立高校受験で求められる学力は、単なる暗記力ではなく:
- 情報を分析する力
- 論理的に思考する力
- 知識を応用する力
こうした「真の学力」です。全統小では、まさにこれらの力を測定する問題が出題されます2。例えば、算数では単なる計算問題だけでなく、複数のステップを要する応用問題が出題され、思考プロセスそのものが評価されます。
公立中学進学予定者が小学6年生の段階でこのような問題に触れておくことは、3年後の高校受験に向けた確かな土台作りになります。
定量的な成長記録としての価値
全統小は年に2回実施されるため、小学6年生の6月と11月に受験すれば、半年間の学力の変化を数値で確認できます2。この「成長の可視化」は、お子様の自信につながると同時に、効果的な学習方法を検証する機会にもなります。
特に「連続受験で学力の伸びを実感しましょう」というキャッチフレーズの通り2、定期的に受験することで、学習方法の効果を客観的に評価し、必要に応じて改善することが可能になります。
全国統一小学生テストを最大限活用するための5つの実践的アドバイス
アドバイス1:過去問を活用した効果的な準備法
全統小を有意義なものにするためには、適切な準備が不可欠です。四谷大塚の公式サイトには「全国統一小学生テスト 過去問チャレンジ」というコーナーがあり、過去に出題された問題を見ることができます1。これらの過去問を活用する際のポイントは:
- 時間を計って解く:実際のテストと同じ時間配分で取り組む
- 間違えた問題を分析:単なるミスなのか、根本的な理解不足なのかを区別
- 出題傾向を把握:どのような形式の問題が多いのかを事前に理解
特に公立中学進学予定者の場合、中学受験向けの特殊な問題にはあまりこだわらず、基礎的な問題の確実な得点と、標準的な応用問題への対応力を重点的に対策するのが効果的です。
アドバイス2:テスト当日のベストな過ごし方
テスト当日は、お子様が最高のコンディションで臨めるよう配慮が必要です。具体的には:
- 前日:十分な睡眠をとる(最低8時間)
- 朝食:脳のエネルギー源となる炭水化物をしっかり摂取
- 持ち物:鉛筆(予備も)、消しゴム、定規、腕時計(アナログ推奨)
- 到着時間:余裕を持って30分前には会場に到着
また、保護者の心構えとして「結果よりもプロセスを評価する」姿勢が大切です。「どれだけ頑張ったか」に焦点を当てることで、お子様がリラックスしてテストに臨めます。
アドバイス3:成績表の効果的な読み方・活用法
テストから約10日後に届く成績表は、単なる順位や偏差値を確認するだけで終わらせてはもったいない貴重な資料です。効果的な活用法としては:
- 「問題別成績一覧」を重点的に分析:正答率が高くて間違えた問題から優先的に復習
- 偏差値の推移を記録:次回受験時の目標設定に活用
- 教科バランスを評価:特定教科に偏りがないか確認
- 子供と一緒に振り返り:まずはできたところを褒めてから改善点を話し合う
ある保護者は「成績表の返却時→褒めてから、前向きな声掛けをする」ことが重要だと父母会で学んだと述べています5。このようなポジティブなアプローチが、子供のやる気を持続させる秘訣です。
アドバイス4:テスト後の効果的な見直し方法
全統小の真の価値は、テスト後の見直しにあります。四谷大塚ではテスト後、以下のようなフォローアップが提供されます2:
- 解説動画:1週間限定で公開されるため、期間内に必ず視聴
- 見直し勉強指導:会場によっては無料で受けられるため積極的に活用
- 苦手単元の重点復習:間違えた問題の類題を市販問題集で練習
特に「見直し勉強指導」では、講師が「三段階前まで遡りながら原因分析」してくれるため7、表面化した間違いの根本原因を突き止めることができます。公立中学進学予定者にとって、このようなプロの指導を受けられる機会は貴重です。
アドバイス5:モチベーション維持のための長期的活用術
全統小を単発のイベントで終わらせず、長期的な学力向上ツールとして活用するためには:
- 半年ごとの目標設定:次のテストまでに克服したい課題を明確に
- 可視化:成績表を目につく場所に貼るなどして意識付け
- 小さな成功を積み重ねる:苦手単元を少しずつ克服する体験を重視
- 保護者の適切な関与:過度な干渉は避けつつ、必要なサポートを提供
教育専門家の西村氏は「テストの結果がどういうものかを親御さんがよく理解しないでネガティブな感情をわが子にぶつけると、お子さんの自己肯定感を下げることになります」と警告しています4。あくまで「成長の機会」として前向きに活用することが大切です。
よくある質問と専門家の回答:公立中学進学予定者のためのQ&A
Q1:塾に通っていなくても大丈夫ですか?
A:全統小は塾に通っていないお子様のために設計されたテストです。四谷大塚は「住んでいる地域や経済的な事情に関係なく、子どもたちに学力向上の機会を広く提供するため」にこのテストを実施していると明言しています2。実際、多くの会場では「対策授業」や「見直し勉強指導」も無料で提供されており、塾に通わない家庭にも配慮がなされています1。
Q2:中学受験の内容が多く出題されると聞きましたが?
A:確かに全統小には中学受験を意識した応用問題も含まれますが、基本は「各学年で習う内容」から出題されます1。公立中学進学予定者は、まず基礎的な問題の確実な得点を目指し、余力があれば応用問題に挑戦するという姿勢で臨むと良いでしょう。無理に全ての問題を解こうとする必要はありません。
Q3:成績が悪かった場合、どのように受け止めれば?
A:教育コンサルタントの宮本氏は「たとえ結果がよくなくても『今のうちの子の力はこんなもんか』と達観することを強くおススメします」とアドバイスしています8。重要なのは、結果を「現在地の確認」と捉え、今後の学習改善に活かすことです。特に小学6年生の場合、中学校進学前に弱点が明確になったことは寧ろ好機と捉えましょう。
Q4:11月のテストと6月のテスト、どちらを受けるべき?
A:公立中学進学予定の小学6年生であれば、11月のテストが特におすすめです。理由は:
- 小学校の全範囲を学習し終えた時期である
- 中学校進学までの時間的余裕があり、弱点補強が可能
- 冬休みを活用した復習計画が立てやすい
6月のテストも有益ですが、11月のテストは中学校進学直前の総仕上げとして特に価値が高いと言えます。
Q5:テスト会場はどう選べば良いですか?
A:会場選びのポイントは:
- 自宅から通いやすい場所:緊張しやすいお子様は特に重要
- 対策授業・見直し指導がある会場:オプションサービスが充実
- 父母会の内容:中学校進学に関する情報が得られるか確認
塾の系列校(四谷大塚直営校や提携塾)を選ぶと、より充実したサポートが受けられる傾向があります1。ただし、どの会場でもテスト自体の内容や成績表の質に違いはありません。
まとめ:公立中学進学予定者こそ受けるべき全統小の本質的価値
全国統一小学生テストは、公立中学進学予定の小学6年生にとって、以下の7つの本質的メリットをもたらす貴重な機会です:
- 全国規模の客観的データで現在の学力を正確に把握できる
- 中学校の学習スタイルへのスムーズな移行を促進する
- 無料で受けられる高品質な学力診断が利用できる
- 学習意欲向上と自己肯定感の育成に役立つ
- 中学校の授業に対応するための基礎力を診断できる
- 親子で取り組む学習習慣確立のきっかけになる
- 高校受験を見据えた長期的な学力育成が可能になる
特に重要なのは、このテストが単なる「学力測定」ではなく、「学力を伸ばすための仕組み」として設計されている点です2。テスト前の対策、テスト中の緊張感ある環境、テスト後の詳細な分析と見直し指導まで、一連のプロセス全体がお子様の学力向上に寄与します。
公立中学進学予定者にとって、小学校最後の年に全国規模の客観的な学力診断を受けることは、中学校生活へのスムーズな移行と、その後の高校受験に向けた確かな土台作りに不可欠です。テスト結果の数字に一喜一憂するのではなく、お子様の長期的な成長を支えるツールとして、全国統一小学生テストをぜひ活用してください。
最後に、教育専門家の西村氏の言葉を借りれば、「お子様の成長に合わせた教育を、ぜひ考えてあげて下さいね」8。全統小はそのための貴重な指針を提供してくれるはずです。お子様の輝かしい未来のために、この機会を最大限に活用されることを心からお勧めします。
府中市・府中第二小学校隣の教育複合施設Clover Hillのご紹介
全国統一小学生テストは、四谷大塚が主催する全国規模の無料学力テストで、お子さまの学力を客観的に測ることができる貴重な機会です。府中市内でも複数の会場が設けられており、お子さまに最適な環境で受験が可能です。
府中第二小学校の隣にある教育複合施設Clover Hillでは、全国統一小学生テストの受験会場として試験を実施するだけでなく、事前対策講座や試験後のフィードバックも提供。受験後は、結果をもとに学習アドバイスを行い、お子さまの学力向上をしっかりサポートします。
また、Clover Hillでは民間の学童保育や認可外保育園、さらに20種類以上の習い事プログラムを提供。学習と遊びをバランスよく取り入れながら、お子さまの可能性を広げる環境が整っています。Clover Hillで、充実した学びと成長の機会を体験してみませんか?
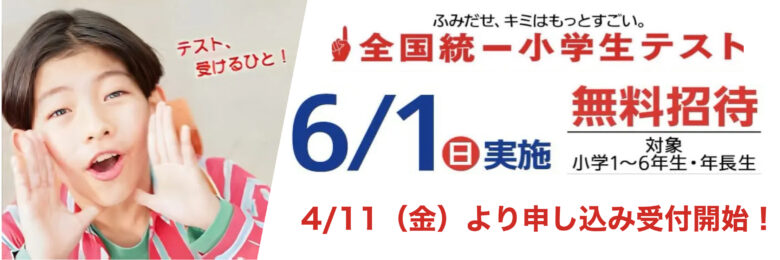
東京都府中市府中市立府中第二小学校となり
教育複合施設Clover Hill
関連記事一覧
- 【府中市】Clover Hillで受けられる全国統一小学生テスト、申込は本日まで!当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 【府中市】Clover Hillで受けられる全国統一小学生テスト、申込は本日まで!
- 【本日含めあと2日】受けないと損する理由。全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 【本日含めあと2日】受けないと損する理由。全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill
- 過去問を活用した効果的な勉強法!全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 過去問を活用した効果的な勉強法!全国統一小学生テスト|府中市の教育複合施設CloverHill
- 全国統一小学生テスト締切迫る!就学前・小学生に今こそ挑戦の機会を|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 全国統一小学生テスト締切迫る!就学前・小学生に今こそ挑戦の機会を|府中市の教育複合施設CloverHill
- 「うちの子に合ってる?」を見える化!年長で受ける全国統一小学生テストの価値|府中市の教育複合施設CloverHill当サイトはGoogleアドセンスによる広告を表示… 続きを読む: 「うちの子に合ってる?」を見える化!年長で受ける全国統一小学生テストの価値|府中市の教育複合施設CloverHill
投稿者プロフィール

-
**Clover Hill(クローバーヒル)**は、東京都府中市にある教育複合施設です。市内最大級の広々とした学童保育、認可外保育園、子供向け習い事数地域No.1を誇る20以上の多彩なプログラムを提供し、子どもたちの学びを総合的にサポートします。
多彩なレッスンの情報や子育て情報を発信しています。
最新の投稿
 府中市の春・夏・冬休み学童保育【完全版】卒園後の預け先リスト!民間学童、一時預かり、ベビーシッターの賢い使い分け|府中市の教育複合施設CloverHill
府中市の春・夏・冬休み学童保育【完全版】卒園後の預け先リスト!民間学童、一時預かり、ベビーシッターの賢い使い分け|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill
府中市 教育・子育て情報「小1の壁」は2月に決まる。学童保育選び、大詰めの今こそ知っておきたい「失敗しない基準」|府中市の教育複合施設CloverHill 府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室
府中市|子供向けカルチャーキッズそろばん教室4月のロケットスタートは2月に決まる!そろばんで作る「新学年0学期」の過ごし方|Clover Hill府中の子供向け人気カルチャーキッズそろばん教室 府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座
府中市|日本速読解力協会・速読解力講座教科書が厚くなる前に。今の学年の積み残しを『速読解力』で一気にクリアする方法|府中市で人気の日本速読解力協会・速読解力講座